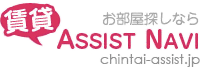空室対策にお困りのオーナー様に耳よりの情報です!
今、ペット共生型物件が流行っているのをご存知ですか?
既存のペット可物件とは違うペット共生型の魅力に、借りたいとの声が殺到しています。
空室に対する対策として今注目のペット共生型物件。


「ペット可にすれば空室の対策になるのはわかっているが、なかには嫌がる入居者もいるのでは?」
「それが原因で他の入居者が退去してしまったら対策どころか元も子もない」
オーナー様からよくそのような言葉をお聞きします。
そんな心配事にも対応したペット共生型賃貸物件のニーズが今、非常に高まっています。
では、果たして空室対策に効くペット共生型賃貸物件とは一体どのようなものなのでしょうか。
よく聞くペット可物件とどう違うのか説明いたします。

建物の所有者および管理会社がペットを飼育することを許可している物件を指します。
あくまでもペットを飼う・飼わないについての選択は入居者に委ねられ、ここがペット共生型と大きく異なります。
そのため、入居者のすべてがペットを飼うことを希望しているわけでもなく、そもそもペット嫌いの入居者が住んでいることもあります。
そのため、入居者同士によるペット飼育をめぐるトラブル(鳴き声や臭いなど)が起きることもしばしばあります。

ペット共生型賃貸物件とは、入居者のすべてがペットを飼うことを前提として考えられた物件を指します。
そのため入居者はペット好きの人がほとんどであり、ペット飼育をめぐるトラブル件数は少ない傾向にあります。
また、ペット共生型物件の共用部分や住居部分にはペット用の水洗などのペット飼育に配慮された設備があることが多いです。
以下はペット共生型でよくみられる設備の一例です。
・ペット飼育に配慮した床材
傷や汚れがつきにくく、手入れのしやすい素材でできています。
また、フローリングと違いすべりにくい素材でできているため、ペットの足腰にもやさしいメリットもあります。
・ペット飼育に配慮した壁材
腰壁式のクロスでは傷や汚れがついたときにも交換がしやすく、なかには消臭機能をもったクロス材もあります。
・飛出し防止ゲート
ペットが玄関から飛び出さないように取り付けられるゲートです。
郵便などのペットにとって不慣れな来客時にも安心して玄関を開けることができます。
・くぐり戸
ペットが自由に行き来できるよう設計された室内ドアです。
冷暖房をつけた部屋の扉でも気軽に閉じておくことができるので、省エネにもなるメリットがあります。
・トリミング室
ペット共生型物件の共用部分に設置されることが多く、ペットの足洗いやシャンプーなどができる場所です。
居室に比べ、ペットの毛などによる配管詰まりにも配慮された造りになっています。
・その他
大きなマンションになると、専用のドッグランを設けていることもあります。
また、建物にトリミングサロンが併設されている物件もあるようです。
こうした理由から一般的なペット可物件よりも飼育に関するストレスが少なく、一度入居したら長期間の入居に繋がるので空室対策に大きく貢献します。


ペット共生型物件の空室対策としての最大のメリットはなんといっても収益性の高さです。
ここからは、なぜ収益性が高くなるのかに注目していきます。

ペット共生型賃貸物件はまだまだ希少価値が高く、競合が多くはありません。
そのため、一度ペット共生型物件として認知されてからは、満室での運用が期待でき、空室対策として効果的です。
また、物件を気に入ってくれた入居者が、別のペット飼育希望者を紹介してくれる事例も対策の1つとなります。
さらに、入居してから退去までの年数も一般的な物件よりも長くなる傾向にある点も空室対策としては優秀です。
埋まりやすく空きにくいという、貸す側にとっては願ったり叶ったりの対策になるのですね。

ペット共生型物件は、その特性から多少割高でも入居をしたいとの声があとを絶ちません。
実際に家賃自体が地域の相場より2割以上もアップしたという実績があり、その収益性の高さに注目が集まっています。

先述のとおり、入居者全員がペット好きということもあり、飼育にまつわるトラブルが起きにくいというメリットがあります。
さらにトラブルを避ける工夫としては『猫のみを飼育可とする』など特定の種別に特化した物件にすることが挙げられます。



ペット飼育に配慮した設備の導入には、一般的なマンションの建築にはないコストがどうしてもかかってきます。
そのため、初期の投資額が多少増加してしまう点には注意が必要です。

初期コストと同様に、維持するためのコストも飼育に配慮した床材やクロス材の張り替えなどにより増加します。
また、入退去の際には飼育時に発生する汚れや臭いを取り除くためのクリーニング費用も割増となります。
とはいえ、維持コストは激増するわけでもなく増えても1~2割程度。
空室期間の短縮・相場よりも高い家賃設定から十分回収が見込める範囲なのでご安心ください。

地域における入居者の絶対数も意識すべきポイントです。
共生型の物件はペット飼育前提の募集をするため、ペットを飼う予定のない人にとってはただの割高の物件という認識です。
同じ地域内ですでにペット共生型の物件が多数散見される場合には、入居者の取り合いになる可能性があります。
また、ペット共生型の物件はその希少性から認知されるまでに少々期間がかかります。
一度認知されれば空室の少ない運用が可能となりますが、そこまでの活動が必要となります。
新聞折り込みやSUUMO・HOME’Sなどのポータルサイトへの出稿に多少費用をかけるべきかもしれません。

ペット共生型物件から、一般の物件あるいはペット可物件に切り替えることはその特性から難しいといわれています。
というのも、ペット飼育前提で入居している入居者に対してのフォロー(家賃の値下げや新しく入ってくるかもしれないペット嫌いの入居者とのトラブルなど)が難しいからです。
同様に、一般の物件あるいはペット可物件からペット共生型物件に切り替えたいという要望にお応えするのも難しいといわれています。
ペット飼育に配慮した設備の導入にコストがかかること、既存の入居者へのフォローが難しいことが理由に挙げられます。
(費用をかけてでもペット共生型にしたいというオーナー様もいらっしゃいますが、それだけ魅力的な運用ということです)

ペット共生型物件はその特性から、ペット可物件よりも細かな細則を定める必要があります。
ペット飼育が前提の建物だからといってすべてを許すわけにはいかないのです。
入居者同士のトラブルを避けるため、最低限下記の事項は定めておく必要があるでしょう。
・繁殖を目的としたペット飼育の禁止
・人間に危害を加える可能性のあるペット飼育の禁止(毒性をもつ、獰猛であるなど)
・多頭飼いの制限(種別・何匹まで可能など)
また、管理会社によってはペット共生型物件の契約条文に対応できない可能性もありますので、事前に確認しておくのが良いでしょう。

ペット共生型物件の魅力についてご理解いただけたでしょうか。
入居者にとってはその条件が、オーナー様にとっては空室率の改善が期待できるとあって、両者にとって大変魅力ある物件となること間違いなしです。
ぜひ一度ご検討ください。